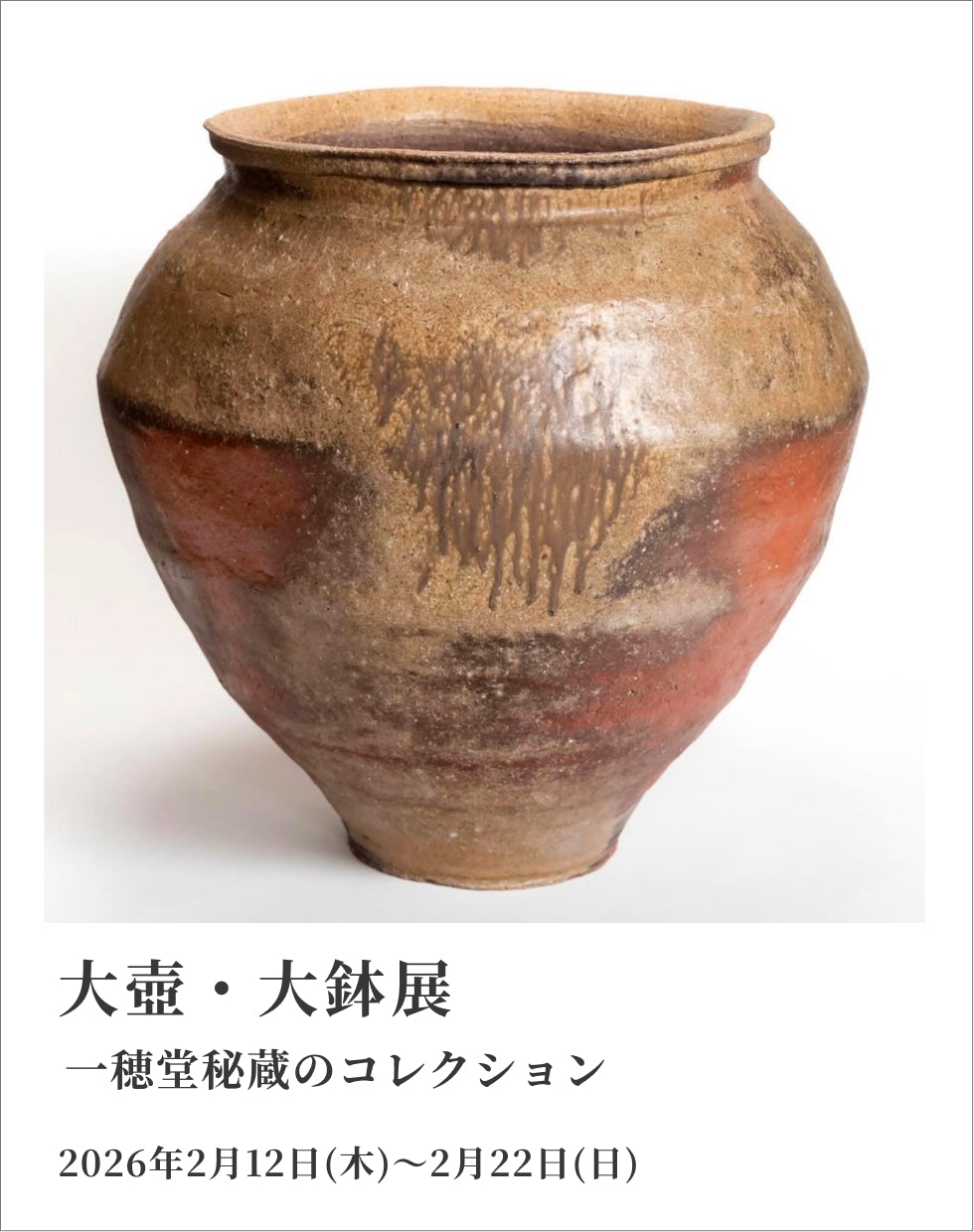コンテンツへスキップ
彫刻をする
石の前に立つ時、石は私に話しかける
石の声はいつも一言である
石は多くは語ってくれない
風の音や虫の声にかき消されるほどの声であるが、
小さな声は力強く何かを伝えようとしている
人の形になる 翼をもつ人になる
音楽を奏でる人になる
家になり丸い石になる
石を通じて自分を捉え、輝く表現を叶えたのだろう。
彫刻をする
「はじめに言葉(ロゴス)があった」。聖書のヨハネによる福音書の冒頭部分には、神の言葉について書かれている。根源的原理は神の言葉であると。私たちの認識している言語は、人間によって生まれた最大の人工物の一つといえるだろう。それでは、その言語が生まれる前、人々はどのように感動を享受し、世界の理を体現していたのであろうか。
アルタミラの洞窟画には、生き物たちの原始的な動きが生き生きと描かれている。また、縄文時代の土器には生活の中で生まれる祈りが“かたち”となったようである。原始、文化というものが、まだ感動と生活の祈りの中に存在した時代には、自然と人間の間で交わされる対話が“かたち”となって表出していた。冨長敦也の彫刻は、この自然と人間の原始的な関わりの中で生まれるエネルギーの対話を彫刻していると言える。
冨長敦也は、イタリアに彫刻を学びに留学した際に、彫刻をすることについて改めて考えることがあった。イタリアの彫刻の歴史は長く、技術も非常に高いモノであった。しかし、それは非常に不自然なかたちで存在していた。技術を求め、技術が目的となる彫刻。ローマ帝国時代、権勢をふるった王たちの頭像を作るために培われていった技巧には、彫刻をする目的が失われていっているようであった。
「彫刻とは何だろうか。」冨長敦也は、彫刻というものが一層分からなくなった。しかし、幼いころに泥だんごを作った自然の中で瞬間に生まれてくる対象と関わる感覚。瞬間の感動。この、ある意味原始的な素材との関わりが、冨長自身の彫刻の在り方と感じ、石のエネルギーを彫りだし、そこに自分の想いをのせる制作を本格的に始めていった。
人の形を捉えた「Ninguen」シリーズ。球体の「Sphere」シリーズ。そして、人々が家の中に存在する「House」シリーズ。すべての作品が、石本来のエネルギーが研鑽されて形になっているかのような作品である。石が我々に語ることば(ロゴス)、そして、石に語らう言葉や想い。この自然と共にある原始的なコミュニケーションが冨長敦也の彫刻には現れている。
「はじめに言葉(ロゴス)があった」。我々が忘れてしまった、言語以前の言葉(ロゴス)が冨長敦也の彫刻から感じ取れる。それは、本来我々が先天的に有している自然の中に存在しているという感覚。この感覚を、石と共生し、彫刻することで洗練され、冨長敦也は唯一無二のプリミティブな彫刻表現をするに至ったのだと言えるだろう。
冨長 敦也
1961 年大阪市生まれ。
1984 年
金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科彫刻専攻卒業
1986 年
金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科修了
1988 年
大阪中之島緑道彫刻公募にて受賞
1997-98 年
ポーラ美術振興財団在外研修助成によりイタリアにて滞在・制作2013 年
第25 回 UBE ビエンナーレ( 山口)にて大賞を受賞
主な個展に
2015 年ときわミュージアム( 山口)
2017 年豊中市立文化芸術センター(大阪)
2024 年長野県立美術館アートラボ
主な活動に
2018 年「公開制作74」府中市美術館
2019 年「真鶴町 石の彫刻祭」( 神奈川)
2024 年「館名石制作」大阪市立東洋陶磁美術館
主なグループ展に
2021 年
「ユニバーサル・ミュージアム―さわる!“ 触” の
大博覧会」国立民族学博物館( 大阪)
2021 年
「 すべての ひとに 石がひつよう」ヴァンジ彫刻庭園美術館( 静岡)
2023 年
「美しい本 湯川書房の書物と版画」神奈川県立近代美術館パブ
リック・コレクション: 長野県立美術館、神奈川県立近代美術
館、ときわミュージアム( 山口)、あさご芸術の森美術館( 兵庫)、LongHouse Reserve(N.Y.)
一穂堂での主な個展
1994 愛宕山画廊
1997 ざくろ坂ギャラリー
2002 銀座一穂堂サロン
2008 年 Ippodo N.Y.( アメリカ)